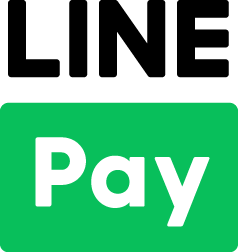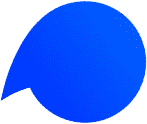この記事はKOMOJUが提供しています。
KOMOJU(コモジュ)は個人から世界的大企業まで様々な事業者が利用している日本の決済プラットフォームです。
スマホアプリを運営していて「ストアの手数料が高い」「自由に決済方法を提供したい」と感じたことはありませんか。近年注目されている「アプリ外課金」は、アプリストアを通さずに外部のWebサイトで課金してもらう仕組みです。
2024年6月に成立し、2025年12月18日に全面施行される「スマホソフトウェア競争促進法」によって、アプリ内から公式サイトに移動し、クレジットカードやPayPayなどで支払いができるようになります。これまでは制限されていた方法ですが、法律の施行によって利用できる決済手段の幅が広がり、手数料を抑えられる可能性があります。
本記事では、アプリ外課金の仕組みやアプリ内課金との違い、法律の影響、メリット、注意点、事例を解説します。アプリ収益を最適化したい方はぜひ参考にしてください。
アプリ外課金とは

アプリ外課金とは、アプリ内の決済システムを利用せず、外部のWebサイトや独自の決済システムで課金を行う方法です。
App StoreやGoogle Playなどのアプリストアを経由しないため、約15〜30%かかるストア手数料を抑えられる点が特徴です。開発者にとっては収益性の向上につながり、価格設定や決済方法、キャンペーン施策を自由に設定できることもメリットです。
ただし、各国の法規制やプラットフォームのガイドラインに沿って導入する必要があります。特に「スマホソフトウェア競争促進法」の影響を理解しておくことが重要です。法律の影響については後述します。
アプリ外課金の仕組み
アプリ外課金は、以下のステップで行います。
【アプリ外課金の流れ】
- ユーザーが決済のためにアプリ内のリンクやボタンをクリックする
- 外部の決済ページに移動する
- 決済ページ上で商品やサービスを選び、決済方法を選択して支払う
- 支払い完了後、アプリに戻ると利用できる状態になる
この仕組みでは、アプリストアを経由せずに課金が完結します。ユーザーにとっては、アプリから外部ページへ移動して支払うため、クレジットカード決済やQRコード決済など希望する手段を選択できます。一方で、決済情報や顧客データの管理は、アプリ提供者の責任です。
アプリ外課金とアプリ内課金の違い

アプリ外課金とアプリ内課金の最大の違いは、「決済処理をどこで行うか」という点にあります。
アプリ外課金は外部サイトや自社システムで行い、アプリ内課金はApp StoreやGoogle Playの決済機能を利用して行います。
アプリ内課金とは
アプリ内課金とは、アプリストアが提供する公式の決済機能を通じて、ユーザーがアプリ内で直接支払う仕組みです。ゲーム内アイテムの購入や機能追加、サブスクリプション型のサービス提供など、多くのアプリで利用されています。
ストア側が決済処理・返金対応・セキュリティ対策を一括で担うため、開発者にとって運用コストを抑えやすく、ユーザーにとっても信頼性の高い支払い方法です。一方で、売上の15〜30%程度を手数料としてストアに支払う必要があるため、収益性に課題が残ります。
アプリ内課金の種類 | 説明 |
消耗型課金(消費型課金) | ゲーム内通貨や回数券など、使うと消費されるアイテム |
非消耗型課金(非消費型課金) | 広告削除や追加機能の解放など、一度購入すれば永続的に利用できるもの |
自動更新サブスクリプション | 動画配信や音楽配信など、定期的に自動課金されるサービス |
非更新サブスクリプション / 分割払い・プリペイド | 一定期間のみ利用可能で、自動更新されない課金方式 |
スマホソフトウェア競争促進法によりアプリ外課金が注目されている
2024年6月に成立した「スマホソフトウェア競争促進法」は、2025年12月18日の全面施行を控えています。この法律が施行されることで、アプリ開発者は外部決済への誘導を行いやすくなります。そのため、アプリ外課金が大きな注目を集めています。
スマホソフトウェア競争促進法とは
スマホソフトウェア競争促進法は、スマートフォンアプリ市場における公正な競争を確保するために制定された日本の法律です。2024年6月に成立し、2025年12月18日に全面施行される予定です。AppleやGoogleなどの大手プラットフォームが、アプリ開発者に一方的に不利な条件を課すのを防ぐことを目的としています。
まず、この法律では大手プラットフォームに対して以下の行為を禁止しています。
- 外部決済システムの利用を不当に制限すること
- 検索順位を自社サービスに有利に操作すること
- 開発者に不当な契約条件を強要すること
これにより、アプリ開発者は外部決済を導入しやすくなり、アプリ外課金を活用できる環境が整いつつあります。ストアの手数料に縛られず、自社の決済方法や独自の料金設計を実装できる可能性が広がっています。
法律の背景には、特定の巨大プラットフォームに依存していた市場構造を改めたいという狙いがあります。従来の独占禁止法では対応に時間がかかるため、より迅速に不公正な取引を規制できる枠組みを整えました。また、アプリ開発の新規参入を促し、ユーザーが多様なサービスを選べる環境をつくることで、イノベーションを促進することも目的の一つです。
現時点では、現時点ではAppleやGoogleといった大手プラットフォームからの具体的な対応は発表されておらず、アプリ事業者にとっては様子見の段階が続いています。2025年12月の全面施工に向けて、動向を注視しましょう。
▶︎参照:スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(e-Gov)
対象のコンテンツ
スマホソフトウェア競争促進法の対象となるのは、すべてのアプリではなく、法律で定められた「特定ソフトウェア」です。具体的には以下の4種類が対象に含まれます。
- モバイルOS(例:iOS、Android)
- アプリストア(例:App Store、Google Play)
- ブラウザ(例:Safari、Chrome)
- 検索エンジン(例:Google検索など)
これらの事業者が「指定事業者」とされた場合、不当な外部決済の制限や検索順位の操作などが禁止されます。その結果、アプリ提供者は外部決済の利用や自社システムの導入がしやすくなるといった間接的な恩恵を受けます。
一方で、ゲームや動画配信、電子書籍アプリといった「課金機能を備えたサービス」は規制の直接対象ではありません。ただし、利用するストアやプラットフォームのルールが変わることで、大きな影響を受ける可能性があります。
アプリ提供者への影響は?
法律の施行により、アプリ提供者は収益モデルを従来より柔軟に設計できるようになります。これは、アプリ外課金を取り入れることで、ストア手数料を削減し、独自の価格設定やキャンペーン施策を展開できるためです。
その一方で、外部決済を導入する場合は以下の対応が必要です。
- 決済システムの構築や決済代行サービスの導入
- セキュリティ対策の徹底
- 問い合わせ・返金対応の体制整備
導入したからといって必ず収益が増えるわけではなく、運用負担とのバランスを見極めることが重要です。また、法律の解釈や実務上の運用は今後も変化する可能性があるため、最新情報を継続的に確認し、適切に対応することが求められます。
アプリ外課金の想定される3つのメリット

アプリ外課金を導入すると、ストア手数料の削減に加え、ユーザーに合わせた決済方法の導入や柔軟な価格設定を実現できます。開発者にとっては、売上の確保とサービス拡張の両面で大きなメリットがあります。
高額な手数料をプラットフォームに支払う必要がない
アプリ内課金を利用すると、App StoreやGoogle Playに売上の約15〜30%を手数料として支払う必要があります。アプリ外課金を導入すれば、このストア手数料を回避でき、売上をより多く自社の収益として確保できます。
外部の決済代行サービスを利用する場合には、一般的に3〜5%程度の手数料が発生しますが、それでも全体の負担は大幅に軽減されます。特にサブスクリプション型サービスや高額課金が発生するサービスでは手元に残る利益が増えやすくなります。
顧客が求める決済方法を提供できる
アプリ外課金を利用することで、クレジットカード決済に限らず、QRコード決済、銀行振込、電子マネー決済など、多様な決済方法を導入できます。これにより、ユーザーに慣れた支払い手段を選んでもらえるため、購入のハードルを下げる効果が期待できるでしょう。
特に若年層ではクレジットカードを持たないケースも多く、国内外の市場を狙うサービスでは決済手段の多様化が重要です。ユーザーに寄り添った柔軟な支払い環境を提供することで、顧客満足度の向上と離脱防止につながります。
自由な価格設定やキャンペーン設計ができる
アプリストアのルールに従う場合、割引率や期間、バンドル販売の条件に制限がかかることがあります。アプリ外課金を導入すれば、自社の判断で価格を柔軟に変更し、期間限定のセールや会員限定の特典を設定できます。こうした施策はユーザーの購買意欲を高め、収益を最大化する有効な手段になるでしょう。
アプリ外課金の想定される注意点
アプリ外課金の導入にあたって、決済フローの設計やセキュリティ対策を怠ると、ユーザー体験や信頼性を損なう可能性があります。以下では主な注意点を解説します。
決済用のWebページを用意する必要がある
アプリ外課金を行うには、アプリストアに代わる決済ページを自社で準備する必要があります。ユーザーが実際に支払いを行う窓口になるため、整備を怠ると購入を途中で諦められたり、トラブルにつながったりする可能性があるでしょう。
実際には、自前でゼロから開発するのではなく、決済代行サービスを利用するのが一般的です。これにより、クレジットカード決済やコンビニ決済など複数の決済手段をまとめて導入でき、セキュリティ対策も一定レベルまで担保できます。
また、決済ページには、ユーザーが安心して購入できるよう、以下の情報をわかりやすく表示することが求められます。
- 商品やサービスの名称と内容
- 価格(税込・税抜)
- 支払い方法と支払いのタイミング
- 提供(引き渡し)の時期
- 返品・キャンセルに関する条件
- 事業者の情報(会社名・所在地・問い合わせ先)
これらを明記しないと「不透明な販売」と受け取られ、信頼性を損なうリスクがあります。特に継続課金型のサービスでは、契約条件を曖昧にしたまま運用すると法的トラブルにつながる恐れもあるため注意が必要です。
決済ページへ誘導の工夫が必要
アプリ外課金では、ユーザーがアプリから外部のWebページに移動して支払いを行います。せっかくアプリ内でスムーズに操作できていたのに、決済の場面だけ急に体験が途切れてしまうと、利便性が損なわれ、離脱や売上機会の損失につながるでしょう。
そこで、決済ページへの誘導は「できるだけアプリ体験の延長線上にある」と感じてもらえるように設計する必要があります。具体的な工夫には次のようなものがあります。
- 購入ボタンを直感的にわかる位置に置くことで、迷わず次のステップに進めるようにする
- 画面遷移を最小限に抑え、数タップで決済ページへ到達できる設計にする
- 「公式サイトで安全にお支払いできます」といった補足メッセージを表示し、不安感を払拭する
こうした工夫を行うことで、ユーザーに「アプリ内でシームレスに買い物が完結した」と感じてもらいやすくなります。逆にここを軽視すると、「アプリなのに使いにくい」と思われ、せっかくのサービス価値を落としてしまう点に注意が必要です。
セキュリティ対策が必要
アプリ外課金では、プラットフォーム(AppleやGoogle)が提供する決済の仕組みを使わないため、開発者や事業者自らがセキュリティを確保する責任を負います。十分な対策を行わない場合、ユーザーの個人情報やカード情報の漏洩につながり、信用を失うだけでなく法的責任を問われる恐れがあるのです。
代表的な対策には以下があります。
- 通信の暗号化:必ずSSL/TLS(https化)を導入して、決済データを安全に送受信する
- PCI DSS準拠:クレジットカード情報を扱う場合は、国際的なセキュリティ基準であるPCI DSSに準拠した仕組みを利用する
- 不正アクセス検知:不正利用や不審な取引を監視し、早期に遮断できる仕組みを導入する
こうした要件を満たさないと、情報漏洩や不正請求によって顧客の離反やブランド毀損、法的ペナルティにつながるリスクがあるのです。決済代行サービスを活用すれば、多くのセキュリティ要件をまとめてカバーできるため、導入をスムーズに進めやすくなります。
▶︎あわせて読みたい記事:クレジットカードの不正検知システムとは?
アプリ外課金を活用している主なサービス
アプリ外課金は、すでに多くの人気サービスで導入されています。いずれもストア手数料を回避しつつ、自社の収益性やユーザー体験を高める戦略をとっています。
Kindle
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindle」は、代表的なアプリ外課金の事例です。電子書籍を購入する際は、アプリ内ではなく、外部のWebサイトで決済が行われます。ユーザーはAmazonのWebサイトで支払いを済ませ、購入した書籍は自動的にアプリに同期されます。
当初はユーザーが自分でブラウザを開いてAmazonの販売ページにアクセスする必要がありましたが、2025年5月には米国のiOS版Kindleアプリに「Get Book」ボタンが導入され、アプリから直接ブラウザへ移動してスムーズに購入できるようになりました。ただし、日本では現時点でこの機能は実装されておらず、引き続きWeb経由での購入が必要です。
Netflix
動画配信サービス「Netflix」も完全にアプリ外課金に切り替わったサービスです。かつてはiOSアプリからApp Storeを経由して登録できましたが、2018年以降はそれをすべて停止し、公式Webサイト経由の決済に一本化しました。
ユーザーはブラウザでクレジットカードやデビットカードを使って決済します。この仕組みによって、AppleやGoogleに手数料を支払わず、自社の収益モデルを構築できています。
モンスターストライク
株式会社MIXIが提供する人気ゲーム「モンスターストライク(モンスト)」は、アプリ内課金とアプリ外課金を併用しているハイブリッド型の事例です。ゲーム内アイテム「オーブ」は従来どおりApp StoreやGoogle Playを通じて購入できますが、公式の「モンストWebショップ」から外部決済で購入することも可能になっています。
モンストWebショップでは、クレジットカード決済やPayPay、楽天ペイ、Amazon Payなど多様な決済手段に対応しています。アプリストアを経由しない分、ユーザーにはお得なボーナスが付与される商品が提供されます。これにより、開発者はストア手数料を抑えることができ、ユーザーは支払い方法や購入特典の選択肢を広げることができる仕組みが整っているのです。
アプリ外課金には決済代行の活用がおすすめ

アプリ外課金を導入する際は、自社でゼロから決済システムを構築するよりも、決済代行サービスを活用するのがおすすめです。既存の決済インフラを利用することで、開発・運用コストを抑えながら、ユーザーに安心で便利な決済環境を提供できます。
決済システム開発の必要がない
決済代行を利用すれば、複雑な決済システムを自社で構築する必要がありません。既存のサービスを導入するだけで、ユーザーがすぐに利用できる決済ページを準備できます。開発期間の短縮やコスト削減につながり、中小規模のアプリ提供者にも適しています。
豊富な決済方法を手間なく導入できる
決済代行サービスを使えば、クレジットカード決済、銀行振込、コンビニ決済、QRコード決済など、多様な決済手段を一括で導入できます。自社で個別に契約・開発する必要がないため、手間を大幅に省けます。ユーザーのニーズに合わせた決済手段を柔軟に取り入れられる点が大きな強みです。
セキュリティの高い決済サービスを利用できる
決済代行サービスは、PCI DSS準拠や不正検知システムなど、国際的なセキュリティ基準に対応しています。自社で同等のセキュリティ対策を整えるのは負担が大きいですが、専門サービスを利用することで安全性を確保できます。これにより、ユーザーが安心して購入できる環境の整備が可能です。
決済データから分析できる
多くの決済代行サービスでは、売上やユーザー属性を分析できる管理画面が提供されています。これを活用することで、ユーザーの購入傾向を把握し、キャンペーンや価格設定に役立てることが可能です。決済手段の提供にとどまらず、マーケティングの改善にもつながります。
まとめ|アプリ外課金の特徴を理解し最適な決済手段を導入しよう
アプリ外課金は、ストア手数料を抑えつつ多様な決済方法を導入できる仕組みです。収益性を高める一方で、決済ページの整備やセキュリティ対策が必要になるため、決済代行サービスを活用するのが効果的です。
決済代行サービス「KOMOJU」は、クレジットカード決済からコンビニ決済、QRコード決済まで幅広く対応し、セキュリティ面も強化されています。アプリ外課金をスムーズに導入したい開発者はぜひご検討ください。
*QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

この記事はKOMOJUが提供しています。
KOMOJU(コモジュ)は個人から世界的大企業まで様々な事業者が利用している日本の決済プラットフォームです。