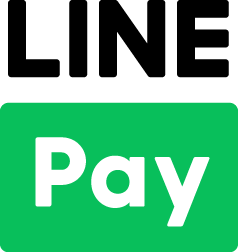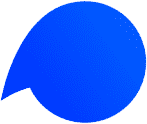この記事はKOMOJUが提供しています。
KOMOJU(コモジュ)は個人から世界的大企業まで様々な事業者が利用している日本の決済プラットフォームです。
ECサイト運営をおこなううえで、カゴ落ちという言葉を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。
カゴ落ち率が高いほど、機会損失額が大きくなるため、売上低下につながります。この記事では、カゴ落ちが起こる原因と対策を分かりやすく解説します。EC事業者で、売上をさらに上げたい人はぜひ最後までご覧ください。
カゴ落ちとは?
カゴ落ちとは、ECサイトで顧客が商品をカートに入れたものの、決済をせずにサイトを離脱する行為です。別名「カート放棄」「カート落ち」「カート離脱」とも呼ばれます。カゴ落ちは、EC運営で売上を上げるために対策すべき課題のひとつです。
カゴ落ちが多いと、クリックに対して購入された割合を表すCVR(コンバージョンレート)が下がってしまいます。株式会社 イー・エージェンシーが2021年4月~2022年9月のカゴ落ちによる機会損失額を調査したところ、ECサイトにおけるカゴ落ちは売上に対して平均2倍の機会損失額を生んでいると判明しました。
参照:<調査報告>ECサイトのカゴ落ち率 イー・エージェンシー
つまり、カゴ落ち問題は、EC事業者にとって避けては通れない問題といえます。
▶あわせて読みたい:【ECサイト運営の基本】業務内容や担当者に必要なスキルを解説
カゴ落ち率の計算式
カゴ落ち率とは、ECサイトに訪れた消費者がどれくらいの割合でカゴ落ちしているかを表す指標です。ECサイトのカゴ落ち状況を把握するためにも、カゴ落ち率の計算方法を知っておきましょう。カゴ落ち率は、下記の計算式で算出できます。
- カートに入れた商品数 – 購入した商品数 = 購入していない商品数
- 購入していない商品数 ÷ カートに入れた商品数 × 100 = カゴ落ち率(%)
カゴ落ち率の平均
世界のECサイトにおけるカゴ落ち率は、アメリカのBaymard Instituteによると2024年の平均は70.19%だそうです。実に7割ほどの商品が、カートに入れられたものの、決済まで至らなかったことが判明しています。
ECサイトの規模が大きいほどカゴ落ちによる機会損失額も大きくなるため、カゴ落ち率をいかに下げられるかがEC運営において重要なポイントです。世界の平均であるカゴ落ち率70%を目安に、前述したカゴ落ち率の計算式を用いて、現状のカゴ落ち率がどれくらいなのか確認してみてください。
カゴ落ちが発生する11の原因と対策

Baymard Instituteが発表した資料によると、カゴ落ちが発生する主な原因は下記の1~10です。カゴ落ちした原因の割合が高い順に記載しています。その他にも考えられる原因1点を合わせ、11の原因とその対策について考えていきます。
| カゴ落ちの原因 | 主な対策 |
1 | 送料や手数料が高い | 送料・手数料など追加でかかる費用を下げる |
2 | アカウント作成が必要 | 会員登録の手間を簡素化する |
3 | クレジットカードの情報を記入したくない | セキュリティ対策について明示する |
4 | 商品が届くまで時間がかかる | 配送方法の選択肢を増やす |
5 | 決済手順が複雑 | 購入までのプロセスを簡素化する |
6 | 購入金額が分からない | 決済前に合計金額が表示されるようにする |
7 | 返品ポリシーに納得できない | 返品や交換条件を明確にする |
8 | 買い物途中でエラーが発生した | サーバーを強化しエラー未然に防ぐ |
9 | 決済方法の選択肢が少ない | 決済方法の選択肢を増やす |
10 | クレジットカード決済時に拒否された | 決済できない原因を明示する |
11 | 買い物途中であることを忘れている | カゴ落ちメールを送る |
それでは、一つずつ見ていきましょう。
1. 送料や手数料が高い
決済する際に想定外の費用がかかることが判明すると、消費者はカゴ落ちしやすいです。商品ページには、販売価格や商品のアピールポイント、配達方法が記載してある場合が大半ですが、送料や手数料など追加費用は把握しにくい場合があります。
【対策】送料・手数料など追加でかかる費用を下げる
対策としては、まず配送会社ごとの送料や手数料を比較することです。法人契約をすれば、送料を抑えられる場合があります。まとめて大量に購入するのも送料のカットにつながるため、消費者が一定額を超えた購入をした場合には送料を無料にするといったことも可能になるでしょう。
また、送り状を紙媒体ではなくインターネット上で発行するのも、費用を抑えるのに効果的です。
2. アカウント作成が必要
商品の決済時にアカウント作成が必要であると、アカウント作成を煩わしく感じて購買意欲がなくなり、ECサイトを離脱する消費者もいます。
一方で、アカウント作成はEC事業者にとっても消費者にとってもメリットがあるため、できるだけ作成してもらうよう工夫することも大切です。EC事業者からすると、メールなどでイベントやキャンペーンを通知しやすく、リピート率が高まります。消費者にとっても一度アカウントを作れば、住所や決済情報などの登録を何度もおこなう必要がなく便利です。
【対策】会員登録の手間を簡素化する
対策として、アカウントがなくても購入できるようにしたり、アカウント作成を簡素化したりする方法があります。名前のふりがなや住所などを自動入力できるようにすると、入力の手間が省けます。また、消費者にとってのアカウント作成のメリットを注意書きに加えておくのも効果的です。アカウント作成すると保証期間が伸びるなど、特典をつけてもよいでしょう。
3. クレジットカードの情報を記入したくない
消費者が商品を購入する際、Amazonや楽天、Yahoo!など有名な媒体ならクレジットカードの情報を記入するのに抵抗はないかもしれません。一方で、あまり知名度がない企業が運営する自社ECサイトの場合だと、セキュリティ面やサービスへの信頼性に不安を抱いてカゴ落ちしてしまう消費者もいます。
【対策】セキュリティ対策について明示する
対策としては、ECサイト内にセキュリティ対策の取り組みについての説明ページを設け、信頼性を上げる方法が考えられます。クレジットカード以外の決済方法に対応しておくことも重要です。
▶あわせて読みたい:クレジットカード不正利用の7つ原因と事業者が行うべきセキュリティ対策
4. 商品が届くまで時間がかかる
昨今はECサイトにおける商品の到着スピードが大幅に早まりました。その分できるだけ早く商品を手に取りたいという顧客ニーズが高まっており、商品が届くまで時間がかかり過ぎるとカート落ちの原因となります。
とはいえ、海外から輸入する商品など、どうしても数日から数週間は時間が必要なケースもあるでしょう。日本国内でも2024年問題で、従来の配達時間より半日~1日ほど長くかかることが見込まれています。
【対策】配送方法の選択肢を増やす
配送方法を複数用意しておけば、消費者がスピードか送料か重視するほうに合わせた選択ができるでしょう。また、商品ページに商品到着までの目安となる日数はもちろん、国外発送であるため時間がかかる旨なども記載し、消費者に理解を求めることも大切です。
5. 決済手順が複雑
決済までのフローが複雑だと、消費者は購買意欲をそがれてしまい、ECサイトを離脱してしまいます。ECサイトの魅力は、手軽かつ簡単に商品を購入できる点です。したがって、決済手順が複雑だとカゴ落ちを招いてしまいます。
【対策】購入までのプロセスを簡素化する
決済手順をいかに簡素化できるかが、カゴ落ちを防ぐポイントです。
一般的には、商品をカートに入れ、配達先の住所や決済方法を入力し、確認画面に移動したら決済が完了します。そのため、住所を郵便番号から自動入力できるようにしたり、クレジットカード番号の入力欄をカードと同じ枠にしてどこにどの番号を入力するか分かりやすくすると、プロセスがスムーズです。手順を購入ページに表示しておき、あと少しで手続きが終わることが分かるようにしておくのもひとつの方法でしょう。
また、d払いのようなアカウント入力だけで支払いが行える決済方法も活用すると、効率的です。
6. 購入金額が分からない
商品ページによっては、決済画面に移動するまで購入金額が分からないケースもあります。消費者は予想より商品の金額が高いと、カートを離脱しほかに安い商品がないか探しにいってしまいかねません。
【対策】決済前に合計金額が表示されるようにする
カートに入れる前の段階で購入金額がはっきり表示されていると、消費者も安心できるでしょう。送料や手数料なども、金額に含まれているのか別途かかるのか明記することが大切です。後から料金が追加されると購買意欲が低下してしまう恐れがあるので、初めから全ての料金を合わせた金額を提示するのが無難です。
7. 返品ポリシーに納得できない
ECサイト内に返品ポリシーが記載されていない、または内容に納得ができない場合にはカゴ落ちとなる可能性があります。消費者にとって、商品に問題があった場合に返品ができるかどうかは重要な点です。
【対策】返品や交換条件を明確にする
消費者が安心して商品を購入できるよう、返品ポリシーはできるだけ詳細を記載する必要があります。返品可能期間は商品に見合った十分な長さを確保し、返品方法も明記しておきましょう。
▶あわせて読みたい:特定商取引法に基づく表記とは? 規制の概要をわかりやすく解説
8. 買い物途中でエラーが発生した
エラーによってECサイトから強制的に離脱させられた場合、そのままサイトに戻らない人もいます。どうしても欲しい商品やキャンペーン中なら再びECサイトに戻ってくる場合もありますが、同じ作業を繰り返す面倒を考えて離脱したままのケースが多いです。
【対策】サーバーを強化しエラー未然に防ぐ
できるだけエラーが起こらないようサーバーを強化したり、定期的に作動状況を確認したりする対策が必要です。サーバーの負荷を軽減するCDNや、セキュリティ対策としてIPSやFirewallを導入しておくとよいでしょう。
9. 決済方法の選択肢が少ない
ECサイトを利用する人の中には、そもそもクレジットカードを保有していない人や、家族会員で購入履歴を家族に知られたくない人などもいます。この場合クレジットカード決済しか選択できないと、カゴ落ちする可能性があります。
【対策】決済方法の選択肢を増やす
決済方法の選択肢を増やす施策が考えられます。スマホ決済やコンビニ決済など、ECサイトをよく訪れる年齢層が使う決済手段に対応しておくとよいでしょう。決済代行サービスを利用すると、複数の決済方法を一括で導入でき、管理も楽です。
▶あわせて読みたい:ECサイトで利用されている主要な決済方法と決済サービスの選び方
10. クレジットカード決済時に拒否された
クレジットカード情報の入力ミスや残高不足などによって決済できず、購入を諦める人もいます。このようなカゴ落ちは、基本的に消費者が原因である場合がほとんどです。
【対策】決済できない原因を明示する
EC事業者は、決済方法の選択肢を増やしたり、何が原因で決済できないのか消費者に知らせたりするのが有効な対策といえます。
11. 買い物途中であることを忘れている
ECサイトの問題ではなく、保存代わりにカートに商品を入れておき、あとで購入するつもりの消費者もいます。そのため、カートに商品を入れたまま、買うのを忘れてしまう場合があります。
【対策】カゴ落ちメールを送る
カゴ落ちメールを送ることが、対策として考えられます。カゴ落ちメールとは、カートに商品が入ったままで買い物がまだ途中であることを消費者に知らせるフォローメールのことです。
初めのタイミングはカートに商品が入った1〜2時間後となるべく早い方が理想的で、回数は当日・3日後・7日後と3回ほどに分けると良いでしょう。消費者がカートに入れた商品のことを覚えていて、かつ必要としているであろう期間が一週間くらいと考えられるためです。
メールを送るタイミングや回数によっては逆に消費者の購買意欲をそぐ恐れもあるため、送りすぎには注意しましょう。
まとめ|カゴ落ち対策として決済方法を増やそう

この記事では、カゴ落ちが起こる原因や対策について解説しました。カゴ落ちが起こる原因のほとんどが、EC事業者側で対策できる内容です。カゴ落ちした消費者は、一度はカートに入れているため、商品に対して少なからず興味を抱いていることを表しています。幅広い決済手段や決済手順の簡素化、フォローメールの送信など、取り組めるカゴ落ち対策は率先しておこないましょう。
ECサイトの決済手段を増やすなら、決済代行サービスを導入することがひとつの方法です。KOMOJUはクレジット決済だけでなく、オンライン決済やコンビニ決済などさまざまな決済手段を一括で導入できます。初期費用や月額費用は0円。導入実績も豊富なため、ECサイトでの売上アップにつながります。
売上サイクルは1週間ですので、キャッシュフローが悪くなる心配もありません。最短即日から利用できるため、カゴ落ち対策として決済方法を増やそうか検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。
【この記事の監修者】

豊田 亮太
グロースマーケター
Shopify Japanの初期メンバーとして、日本市場におけるShopifyの普及に貢献。ECプラットフォーム、決済代行サービス等に関して豊富な知見を持つECのエキスパート。LinkedInページ:https://www.linkedin.com/in/ryota-toyoda-b45127138/

この記事はKOMOJUが提供しています。
KOMOJU(コモジュ)は個人から世界的大企業まで様々な事業者が利用している日本の決済プラットフォームです。